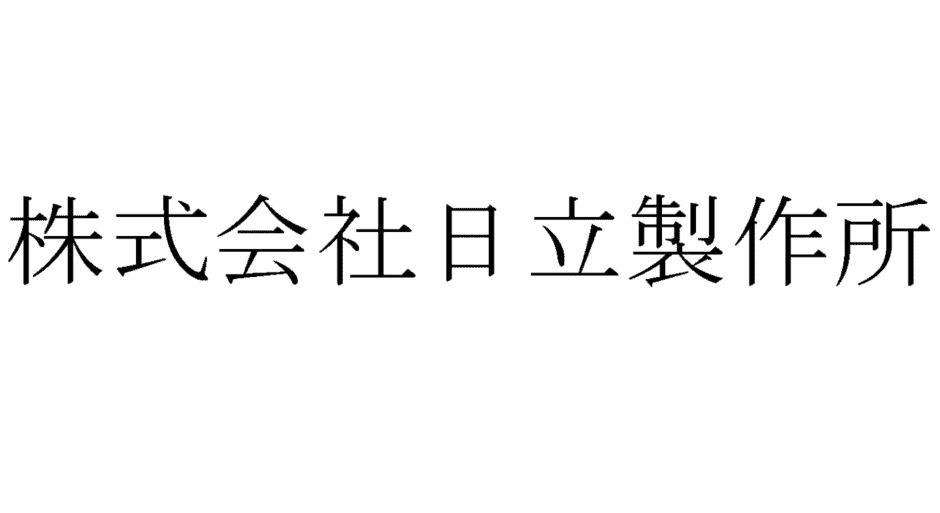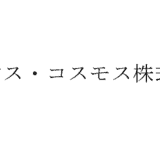株式会社日立製作所は、日本を代表する総合電機メーカーとして幅広い領域で事業を展開しており、ITソリューションや社会インフラなど多岐にわたる分野で活躍できる魅力的なフィールドを提供しています。とりわけシステム開発職では、社会的な影響力の大きい案件に携わるチャンスが多く、技術者としての成長を志す方々にとって人気の高い就職・転職先です。
その一方で、日立製作所の選考では一定の通過率の低さが見られ、最終面接まで進んだにもかかわらず不採用となるケースも珍しくありません。丁寧に準備をして臨んだものの、「なぜ落ちたのか分からない」「あと一歩だったのに」という声も多く聞かれます。
この記事では、日立製作所のシステム開発職における面接について、通過した人・落ちた人それぞれの傾向を分析し、さらに仮想体験談やよく聞かれる質問とその対策までを詳しく紹介します。これから面接に臨む方、過去に不採用となって悩んでいる方のヒントとなる情報をお届けし、最終的には自分に合った転職活動を進める一助となることを目指します。
株式会社日立製作所の面接で通過した人に見られる傾向(要約)
日立製作所のシステム開発職における選考を通過した人には、いくつか共通する特徴が見られます。まず、志望動機が「なぜ日立でなければならないのか」にまで深掘りされており、企業理解や業務理解の深さが感じられる点が挙げられます。ただのイメージや一般論ではなく、日立のプロジェクト特性や技術的強みと、自分の経験・スキルとの接点を明確に語れることが好印象につながっているようです。
次に、過去の経験や成果をもとに問題解決能力やチームでの役割を語る場面で、エピソードの展開に一貫性と論理性があることが評価されています。「なぜそうしたか」「どう行動したか」「どんな結果につながったか」という構造が明確な場合、説得力が増し、選考官からの深掘りにも自信を持って対応できています。
また、面接時の雰囲気に関しては、和やかだったという声もある一方で、圧迫と感じるような厳しい質問が投げかけられることもあります。そうした場面でも、感情に流されず落ち着いた対応ができていることが、人物面でもプラス評価につながっていると考えられます。
最後に、逆質問の質も重要視されています。実際の事業内容やキャリアパスに対する具体的な質問を通じて、志望度の高さや主体性を伝えることができた応募者ほど、面接官に強い印象を残しているようです。
株式会社日立製作所の面接で落ちた人に見られる傾向(要約)
一方で、面接で不採用となった応募者に共通する傾向も明確に見られます。もっとも多かったのは「志望動機が浅かった」「具体性に欠けた」というフィードバックであり、他社でも通じそうな抽象的な内容に終始してしまうと、日立ならではの志望理由が伝わらず評価を得にくいようです。
特に「なぜ日立か」「なぜSEか」という問いに対して、説得力のある回答ができなかったケースでは、最終面接まで進んでも不採用となる事例が複数見られました。また、業務内容や募集ポジションの理解が不十分なまま面接に臨んでしまい、的外れな発言になったことが不採用の一因になっているケースもあります。
さらに、質問に対する回答が曖昧だったり、論理的に話が展開できていなかったりする場合も評価が下がる要因となっています。過去のエピソードを語る中で、成果や具体的行動に触れず印象が薄くなってしまったり、職務経歴の内容を曖昧にしか説明できなかったりする応募者は、面接官に「準備不足」「伝える力が弱い」と受け取られてしまいます。
また、緊張や準備不足から会話がかみ合わず、質問意図を読み違えたり一問一答になってしまったりしたことも、通過率を下げる一因となっています。面接対策が自己完結型になっていると、こうした「ズレ」が生じやすくなるため注意が必要です。
仮想体験談:業界未経験の挑戦、志望動機の浅さが命取りに
私はもともとメーカー系の営業職をしており、30代に入ってからエンジニアへのキャリアチェンジを決意しました。独学でプログラミングを学び、実務経験こそ少ないものの、社内システムの改善に関わった実績をアピールポイントとして、日立製作所のシステム開発職に応募しました。大企業で社会インフラに関われる点や、技術志向の強い環境に惹かれていましたが、正直なところ「日立じゃなきゃダメな理由」は曖昧なままでした。
面接はオンラインで、現場のエンジニアと人事の2名が参加されていました。雰囲気は決して冷たくはありませんでしたが、質問は非常に具体的かつ本質的で、特に「なぜ日立でなければならないのか」「現職でのシステム改善経験を、当社の開発業務にどう応用できると思うか」といった深掘りが続きました。私はそれなりに準備していたつもりでしたが、相手の問いに対し曖昧な言葉で答える場面が多く、自分でも「言葉が宙に浮いている」と感じました。
特に印象的だったのは、「日立が進める社会イノベーション事業についてどう思いますか?」という質問に対して、具体的なプロジェクト名も知らず、「社会に貢献したいからです」とだけ答えてしまった場面です。面接官の表情は変わりませんでしたが、その瞬間から会話の温度が少し下がったような気がしました。
面接後の手応えは正直ありませんでした。そして数日後、あっさりと「今回はご縁がなかった」との連絡が届きました。あのとき、自分の答えがどこまで伝わっていたのか、いま思い返しても悔しさが残ります。
振り返ると、私は日立という企業への理解が浅く、「なんとなく有名だから」「安心して働けそうだから」という理由で臨んでしまっていました。技術職としての志望であれば、企業の取り組みやプロジェクトに対して、自分がどう関われるか、どう価値を発揮できるかまで突き詰めておくべきでした。また、業務経験の浅さを補うために、もっと具体的な成果や学習内容を交えて語るべきだったと反省しています。
今回の不採用を通じて、「面接は相手との対話であり、熱意と準備が見透かされる場」だと痛感しました。次こそは、単なる憧れではなく、論理と根拠をもって企業と向き合えるように、準備の質を見直していきたいと思います。
仮想体験談:社内SEからの転身、技術理解の甘さと質問の読み違えで撃沈
私は20代後半の女性で、これまで5年間、メーカー企業の情報システム部門で社内SEとして働いてきました。業務改善のためのシステム導入や、ベンダーコントロールの経験を積む中で、もっと開発の上流から関わる仕事がしたいと考えるようになり、日立製作所のシステム開発職に応募しました。
選考は書類とWebテストを通過し、一次面接はオンラインで実施されました。面接官は人事と現場のマネージャーで、落ち着いた雰囲気の中で進みましたが、質問の内容はかなり技術寄りでした。「これまで導入したシステムの構成を説明してください」「そのときにパフォーマンスやセキュリティ面で意識したことは?」と聞かれ、正直、焦りました。
私は開発現場というより、ユーザー部門との橋渡し役に近いポジションだったため、技術的な部分はベンダー任せにしていたのが実情です。そのため、話す内容がどうしても抽象的になり、面接官の深掘りにうまく応えられませんでした。
特に、「当社のような大規模案件で求められる開発プロセスをどうイメージしていますか?」という質問に対し、私は「ユーザーの要望を丁寧にヒアリングすることが大事だと思います」と答えてしまい、面接官から「それは要件定義の初期段階の話ですよね。その後の工程についてはどうお考えですか?」と返され、完全に詰まりました。
面接後、明らかに手応えはなく、3日後には「今回は見送り」との通知が届きました。結果を受けて最初に思ったのは、技術職として応募している以上、開発の具体的なプロセスや技術要素についての理解が甘かったということです。業務経験があるという自負が裏目に出て、「自分はわかっている」という前提で準備を進めてしまっていました。
また、質問の意図をしっかりと読み取る力も足りていなかったと感じています。質問の背景や、面接官が何を見ようとしているかを考える余裕がなく、表面的な答えに終始してしまったことが、不採用につながった最大の原因だったと思います。
今回の面接を通じて、改めて「話す内容の深さ」と「相手視点での応答力」が技術職の面接では問われることを痛感しました。次のチャレンジでは、実績だけでなく技術的な背景知識も含めて、自分の強みを筋道立てて伝えられるように準備していきたいと思います。
仮想体験談:理系院卒、技術偏重のアプローチが裏目に
私は情報系の大学院を修了し、新卒で日立製作所のシステム開発職を志望しました。研究では機械学習のモデル開発に取り組んでおり、その知識を社会実装の現場で活かしたいという思いから、大規模なシステム開発に関わるチャンスのある日立を志望しました。ESと適性検査は順調に通過し、いよいよ最終面接に進むことになりました。
最終面接はオンラインで、技術部門の部長クラスと人事の方の2名が面接官でした。緊張はしていましたが、自分の研究内容や技術へのこだわりについては自信があったので、資料も用意して臨みました。
面接序盤は自己紹介と志望動機から始まり、比較的スムーズに進みましたが、途中から面接官の質問が「チームでどのように研究を進めたか」「関係者と意見が食い違ったときにどう対処したか」といった協調性や対話力に関する内容に変わっていきました。私は正直、研究のほとんどを一人で進めてきたため、そうした経験が乏しく、具体的なエピソードが出せませんでした。
さらに、「当社のプロジェクトは多くの部門をまたいで進められますが、その中であなたはどう貢献できると思いますか?」という問いに対しても、「技術的な専門性を活かして問題解決に寄与したい」と繰り返すだけで、協業や業務理解といった観点まで言及できなかったのは今でも後悔しています。
結果は1週間後、不採用の通知でした。正直、研究成果や技術力には自信があっただけにショックでしたが、面接中の違和感には気づいていました。自分の話す内容が一方通行で、面接官の期待する「現場での適応力」や「コミュニケーション力」に応えられていなかったと反省しています。
技術が好きであることは間違いありませんが、現場では一人で完結することはなく、むしろ「人との接点でどう貢献できるか」が見られていたのだと理解しました。今後は、専門性だけでなく、それをどうチームやプロジェクトに活かせるかという視点を持ち、面接でもそのバランスを意識して臨みたいと思います。
仮想体験談:経験豊富ゆえの思い込み、対話のズレが致命的に
私は40代前半の男性で、これまでシステム開発会社やSIerで20年ほどのキャリアを積んできました。直近では小規模プロジェクトのリーダーも任されており、次はよりスケールの大きいフィールドで自分の経験を活かしたいと考え、日立製作所の中途採用に応募しました。転職はこれで2回目で、今回が最後の転職にしたいという思いもあり、準備にもかなり力を入れていました。
書類とWeb面接を経て、最終面接に進むことになりました。面接官は部門の部長クラスの方と人事の2名。開口一番に「これまでのマネジメント経験について教えてください」と聞かれたので、自分がこれまで率いてきたプロジェクトの規模や管理手法について詳しく説明しました。ただ、話が長くなりがちで、面接官の反応も淡々としており、早く次の質問に移りたそうな雰囲気を感じました。
印象的だったのは、「日立の文化の中で、あなたがこれまでやってきたやり方をどう適応させていくつもりですか?」という質問でした。私は「自分のマネジメントスタイルをそのまま活かしたい」と正直に答えたのですが、今思えばそれが良くなかったのだと思います。面接官からは「当社ではチーム内の合意形成や現場主導が重視されます」とだけ返され、そこで会話が終わってしまいました。
また、逆質問の場面で「評価制度の透明性について教えてください」と質問したところ、「まずは業務に順応することが最優先です」とピシャリと返されてしまい、少し気まずい空気になってしまいました。自分では積極的に質問したつもりでしたが、求められていたのはもっと事業内容に踏み込んだものだったのかもしれません。
結果は翌週にメールで届き、不採用とのことでした。準備もしてきたし、実績にも自信があっただけにショックは大きかったですが、今思えば「経験があるから大丈夫」という姿勢が強すぎたように感じます。面接は一方的に実績を語る場ではなく、相手の価値観に寄り添いながら対話することが大切だということを学びました。
これからは、どんなに経験があっても「この会社で働くならどう振る舞うべきか」を柔軟に考えること、そして自分のやり方だけに固執しない姿勢を意識していきたいと思います。技術力だけでなく、対話力と適応力のバランスが、転職成功のカギだと痛感しました。
仮想体験談:働き方重視の転職、価値観のすれ違いでチャンスを逃す
私は30代前半の女性で、育児との両立をしながら中小IT企業で開発エンジニアとして働いてきました。時短勤務で働く中でも設計からテストまで一通り経験し、子どもが保育園に慣れてきたタイミングで、より安定した環境と大規模案件での成長を求めて日立製作所の中途採用に挑戦しました。
面接までは順調に進み、一次面接はオンラインでの実施でした。面接官は現場のマネージャーと人事担当の2名で、雰囲気自体は丁寧で穏やかでしたが、質問の内容はやや踏み込んだものでした。「今後どのような働き方を想定していますか」「急な業務変更があった場合どう対応しますか」といった質問が続き、私のライフスタイルと業務の柔軟性に関して慎重に見極めようとしている印象を受けました。
私は正直に、「子育てと両立しながら長く働きたい」「急な残業や休日対応は難しい」と伝えたのですが、その後の面接官の反応は少し硬くなったように感じました。技術的なスキルや業務経験についても質問はされましたが、あまり深掘りはされず、時間の多くは働き方に関するやり取りに費やされていたと思います。
面接後、正直なところ違和感が残りました。「こちらの事情にばかり焦点が当たってしまったな」と思いながらも、誠実に話したことは間違っていないと信じたかったのですが、数日後に届いた結果は不採用でした。
振り返ってみると、相手にとって「配慮すべき条件が多すぎる」と受け取られてしまった可能性が高いと感じています。もちろん、家庭の事情は変えられない部分もありますが、伝え方や順序にもう少し工夫が必要だったと反省しています。たとえば、「限られた時間でも成果を出してきた具体的な事例」や「チーム貢献の姿勢」を先に示してから条件を伝えれば、印象は違ったのかもしれません。
今回の経験を通じて、「条件を伝えること」と「信頼される話し方」は別物であることを学びました。自分の制約だけでなく、その中でどう会社に貢献できるかを先に示すことが、面接では何より大切なのだと実感しています。
Q. なぜ日立製作所を志望したのですか?
A. 他社との違いを明確にし、日立の事業領域・技術力・社会貢献性などに対する具体的な理解を示したうえで、自分の経験や志向とどこで重なるかを丁寧に説明すると良いです。
Q. チームで課題に取り組んだ経験を教えてください。
A. チーム内で自分がどのような役割を担い、何を意識して行動したかを具体的に述べることが重要です。特に意見の違いやトラブルがあった際の対処と、結果としてチームにどう貢献できたかを含めると効果的です。
Q. 現在注目しているIT技術やトレンドはありますか?
A. 興味のある技術だけでなく、それが日立の事業にどう活かせるかまで言及できると好印象です。単なる知識披露ではなく、自分なりの視点で語れるかがカギになります。
Q. これまでに直面した課題と、それをどう乗り越えたかを教えてください。
A. 困難な状況をどう捉え、どのような行動をとり、結果として何を学んだかという構成で語ると説得力が増します。問題解決力や主体性、冷静な判断力などをアピールする機会です。
Q. ご自身の強みと、それを業務でどう活かせると考えていますか?
A. 単なる自己PRに終始せず、業務の具体的な場面を想定しながら「このような場面でこの強みが発揮される」という形で実践性を持たせると、面接官の理解も深まります。
Q. 日立のどの事業やプロジェクトに関わりたいと思っていますか?
A. 公共、社会インフラ、DX関連など、日立の注力分野を把握したうえで、自分が関心を持つ理由と、どのように貢献したいかを具体的に述べると志望度の高さが伝わります。
Q. ほかに応募している企業や併願状況を教えてください。
A. 他社の名前を挙げる場合でも、あくまで業界や職種への軸の一貫性を示すことが重要です。最終的に「その中でも日立を第一志望として考えている理由」を補足できると安心感を与えます。
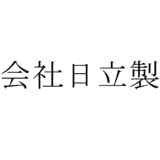 日立製作所の面接や最終面接に落ちた方の体験談【経理職編】
日立製作所の面接や最終面接に落ちた方の体験談【経理職編】 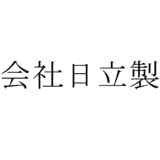 日立製作所の面接や最終面接に落ちた方の体験談【プロジェクトマネージャ編】
日立製作所の面接や最終面接に落ちた方の体験談【プロジェクトマネージャ編】 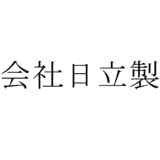 日立製作所の面接や最終面接に落ちた方の体験談【法人営業編】
日立製作所の面接や最終面接に落ちた方の体験談【法人営業編】
面接で落ちて後悔しないために
さて、ここまでこの記事をお読みいただいたあなたは、これから就職や転職を考えている方、あるいはすでに面接を控えている方だと思います。そして、就職や転職活動において事前準備をしっかりと行うことは非常に重要なので、その準備のためにこのブログをじっくりと読んでいただいているのだと思います。
そして、落ちた方のエピソードをまとめていた中で、気づいたことがあります。
それは、
企業研究や自己PRなどの事前準備はしっかりできていても、圧倒的に面接の練習が足りず、面接に落ちてしまったケースが多かった
ということです。
対人相手に実際に話してみる経験を積むことは非常に重要です。

自分の頭の中で「こう話そう」とシミュレーションするのは簡単ですが、それを実際に相手に伝えることは全く別のスキルです。
特に、面接の場では緊張やプレッシャーも影響し思うような受け答えができず落ちてしまうケースが非常に多いです。
今回の記事には書ききれなかったエピソードも多々ありますが、共通して感じたのは「圧倒的に面接の練習が足りない事が原因で落ちてしまい、後悔している方が非常に多かった」ということです。

「企業研修はばっちり」「説明会にも参加しました」と、準備を万全にして臨んでも、面接の練習が足りず、自身の実力や思いを伝えることが出来ずに不合格で終わってしまうことが多々あります。
そのため、内定を獲得するために面接の練習を実践に近い形で行うことをお勧めしますが、家族や友人に面接の練習をお願いするというのはお勧めしません。
家族や友人もこちらが満足するまで何時間も面接の練習に付き合ってくれる訳ではないでしょうし、仮に付き合ってくれたとしてもこちらが気を遣ってしまいますよね。本当はもっとやりたいのに遠慮して「もう大丈夫」と言ってしまうかもしれません。
それに、家族や友人は面接のプロではないので、適切なフィードバックを受けるのは難しいです。
 やはり本気で準備をして内定を獲得したいのであれば、気兼ねなく自分が納得できるまで何度も面接の練習ができる転職のプロの方に相談した方が安心できますよね。
やはり本気で準備をして内定を獲得したいのであれば、気兼ねなく自分が納得できるまで何度も面接の練習ができる転職のプロの方に相談した方が安心できますよね。
従って、本気で内定を獲得したいのであれば、転職のプロである転職エージェントの活用をすることをお勧めします。転職エージェントは就職活動や転職支援のプロフェッショナルです。転職を成功させるための面接対策について、客観的かつ合理的なアドバイスをしてくれます。
彼らは「転職」「就職」を成功させることを仕事にしており、あなたが面接に合格することが彼らの成果となり、それで転職エージェントの方はお金をもらっているのです。
彼らは私たちを紹介する事でお金をもらっているので、お金が欲しいから私たちを受からせたいのです。面接の練習を何回もしてでも、私たちに内定を獲得して欲しいのです。

あなたが合格する事が転職エージェントの目標であり、そのために、真剣に、そして全力でサポートしてくれます。
転職エージェントを使うことで、自分の弱点をプロの視点から分析し、内定を獲得するチャンスが得られます。
しかも、転職エージェントは私たちが内定を獲得する事でお金をもらうことが出来るので、私たちはお金を一切払う必要がありません。
転職のプロに面接の練習をお願いすることが内定の一番の近道ですし、しかも無料…お得なのでぜひやった方が良いですし、そんな彼らを使わない理由は全く無いですよね。
転職エージェントは無料で活用できるため、プロのサポートを無料で受けられるこの機会を活かさない手はありません。成功への一歩を確実にするためにも、転職エージェントに登録することを強くお勧めします。
📌 特におすすめの転職エージェントはこちら
👉
👉
あなたの転職活動が成功し、理想のキャリアを築けることを心から願っています。
「私も落ちた」「こんな質問に困った」——そんなエピソードも大歓迎です。経験を共有することで、次の誰かが自信を持てるかもしれません。ご協力いただける方は、ぜひコメント欄や問い合わせフォームからお気軽にお送りください。
※投稿された内容は、記事の中で「仮想体験談」や「面接傾向」として参考にさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。また、お寄せいただいた内容は編集の上、匿名で掲載させていただく場合がございます。