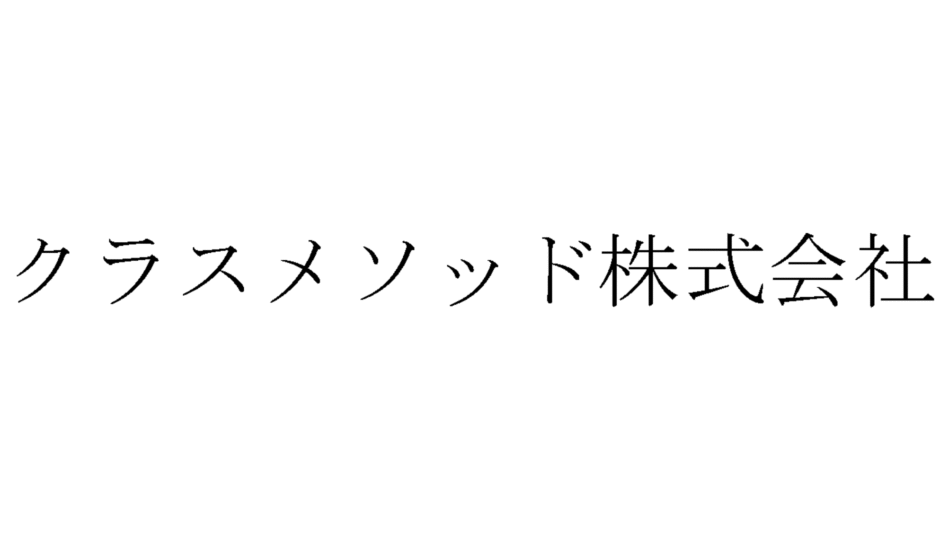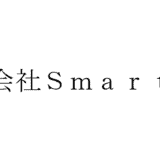「クラスメソッドの面接、落ちた…」そんな経験をされた方は少なくありません。
クラスメソッド株式会社はAWSをはじめとするクラウド分野に強みを持ち、技術力とアウトプットを重視する企業としてITエンジニアから注目されています。
一方で、採用基準は明確でありながらも独特なポイントがあり、対策が不十分だと実力があっても通過は難しいという声も見られます。
この記事では、面接を経験した方の声をもとに、通過した人・落ちた人に見られる傾向、よくある質問とその対策などを整理しながら、読者が次の選考で後悔しないためのヒントをお届けします。
最後には、転職活動をより効果的に進めるためのサポート手段として、転職エージェントの活用についてもご紹介します。
クラスメソッド株式会社の面接で通過した人に見られる傾向
クラスメソッド株式会社の面接を通過した人に共通するのは、技術への強い関心と、具体的なアウトプット経験を言語化できる力です。
たとえばAWS関連の資格を保有していたり、個人・業務問わず何らかのプロジェクト経験をブログやGitHubなどで公開していたりと、技術力を裏付ける実績が見られるケースが多くなっています。
また、録画形式の動画面接やオンライン面談でも、相手の質問の意図を正確にくみ取り、簡潔かつ論理的に返答できるコミュニケーション能力が評価につながっている傾向があります。
さらに「なぜクラスメソッドか」という問いに対して、自分のキャリアと結びつけて回答できることも重要です。
技術志向の高い企業文化を理解した上で、自分がどのように貢献できるかを語れる人材が、選考を突破していると考えられます。
クラスメソッド株式会社の面接で落ちた人に見られる傾向
落選者に見られる傾向として多く挙げられているのが、自己理解の浅さと、準備不足による回答の曖昧さです。
録画面接では緊張や不慣れから、自分でも何を話しているのか分からなくなってしまったという声が複数見受けられました。
また、技術的な質問に対して回答がぼんやりしてしまったり、相手に要点が伝わらず「つまりこういうことですか?」と聞き返されたという体験談もあります。
これらは、事前に想定質問と回答の台本を準備しなかったことや、伝え方の練習不足に起因していると考えられます。
さらに「なぜこの会社を志望したのか」という質問に対し、他社でも通用するような一般的な答えしか用意できていないと、熱意が伝わらず選考通過は難しくなります。
技術が好きであることは前提として、それをどのように実務や会社の方向性と結びつけられるかが問われる面接であることを意識する必要があります。
仮想体験談:業界未経験の挑戦、志望動機の浅さが命取りに
前職では小規模な社内SEとして業務システムの保守を担当していましたが、よりクラウド領域で成長したいと考え、AWSに強みを持つクラスメソッドへの転職を決意しました。
独学でクラウドプラクティショナーを取得し、UdemyでいくつかのAWSハンズオン講座を受講。正直なところ「まだ実務経験はないけれど、ポテンシャルで見てもらえたら」と期待していました。
一次面接は録画形式の自己紹介動画提出と、オンラインでの技術面談でした。動画は自分のスマホで何度か撮り直して提出しましたが、自信のある話し方までは練習しきれず、ややテンポが悪かったように感じます。
技術面談では「どんなAWSサービスを使ったことがありますか?」「最近気になっている技術は?」と聞かれましたが、模範的な答えを用意していなかったため、思いつく範囲で話すしかありませんでした。
雰囲気自体は丁寧でしたが、面接官が何度か「つまりこういうことですか?」と話を整理してくる場面があり、うまく伝わっていないことを実感しました。
特に痛感したのは、志望動機について「なぜ他社ではなくクラスメソッドか」と問われた際、答えが曖昧になってしまったことです。「AWSに強いから」「ブログをよく読むから」程度しか言えず、自分でも説得力に欠けると感じました。
面接の数日後、メールで不採用の通知が届きました。正直、驚きはありませんでした。
今振り返ると、面接そのものよりも、事前準備の浅さが最大の敗因だったと感じます。アウトプットや技術ブログといった「見せられる実績」が乏しく、志望理由も表面的だったため、企業側が「この人を採りたい」と思う決め手がなかったのだと思います。
今後は、実務や個人開発での取り組みを小さくても発信していくとともに、志望企業ごとの特性に合わせて動機をしっかり言語化することの大切さを忘れないようにしたいです。
仮想体験談:ベテランエンジニアの油断、技術力だけでは届かなかった
私はインフラエンジニアとして約12年の経験があり、主にオンプレミスからAWSへの移行プロジェクトを数件担当してきました。
クラスメソッドの技術ブログを読んで興味を持ち、自分のキャリアの集大成として「技術が評価される環境」でさらに挑戦したいと考え、応募を決めました。
面接前の準備では、自分の担当プロジェクトの事例やトラブル対応の話などをメモして整理。技術面は強みがある自負があり、特に不安もなく本番を迎えました。
一次面接はオンラインで、現場エンジニアの方と人事の方が同席して進行。技術的な質問も多く、これまでの経験について詳しく深掘りされました。
たとえば「特に苦労した構築案件は?」「どういった判断軸でサービス選定したか?」など、実務レベルの話が中心で、手応えは正直ありました。
ただ、その後に続いた「普段どんな情報発信をしていますか?」「会社ブログへの参加に抵抗はありますか?」という問いかけに、少し戸惑いました。
私は業務に集中してきたタイプで、外部への発信や社外登壇などはしてきておらず、そういった文化にあまり関心を持っていなかったからです。
また、企業カルチャーへの共感を問う質問も多く、「変化を楽しめるか」「個人での裁量をどう感じるか」など、いわゆる“技術力のその先”を見られている印象を受けました。
面接後、数日で結果通知が届き、不採用とのこと。納得しきれない気持ちもありましたが、冷静に振り返ってみると、カルチャー面のフィット感をうまく伝えられなかったと反省しています。
クラスメソッドは、単なる技術者集団ではなく「学ぶ・発信する・共創する」文化を大事にしている企業だと改めて感じました。
今後は、自分の技術力に頼るだけでなく、それをどう社外に伝えるか、仲間と共有していくかといった視点を持ちたいと思います。技術以外の価値観にもアンテナを張ることの重要性を、今回の面接で学びました。
仮想体験談:キャリアの軸が定まらず、熱意が伝わらなかった
新卒で入社したSIerでは、2年間インフラ関連の運用保守業務を担当していました。
決まった手順書通りの作業が多く、自分で設計や構築に関わる機会がなかったことから、もっと裁量のある環境でスキルアップしたいと思うようになりました。
そんなとき、クラスメソッドの採用ページを見つけて、技術志向の強い社風やAWS特化の取り組みに惹かれ、思い切って応募しました。
初めての転職活動だったこともあり、履歴書や職務経歴書の書き方からネットで調べながら準備。動画面接もあったので、何度か自撮りで練習してから提出しましたが、正直これで良いのか分からないまま本番を迎えました。
一次面接はオンラインで、人事と現場エンジニアの方が参加されました。雰囲気は和やかでしたが、「今後どんなインフラエンジニアを目指しているか?」「技術をどう磨いていきたいか?」という質問に、うまく答えられませんでした。
自分の中でキャリアの方向性がまだ定まっていなかったため、「もっと成長したい」「手を動かす仕事がしたい」など、抽象的な言葉ばかりになってしまったのです。
さらに「最近触っている技術や学習している内容は?」と聞かれた際、うまく話がつながらず、質問の意図とずれた返答をしてしまった気がします。
結果は翌週に届き、不採用とのことでした。
今回の選考を通じて痛感したのは、「なぜ転職したいのか」「どう成長したいのか」という自分なりの軸が曖昧だと、企業に響かないということでした。
クラスメソッドは、自発的に学び、発信し、成長していける人を求めていると感じます。そのためには、まず自分自身の方向性を明確にし、言葉にできるよう準備する必要があったと反省しました。
次は、目指したい姿や自分が何を大切にしたいかを掘り下げた上で、企業選びや面接に臨みたいと思います。
仮想体験談:管理経験が裏目に、求められたのは“手を動かす技術者”だった
私は40代前半で、これまで複数のシステム開発会社にてインフラチームのマネージャーを務めてきました。
直近では10名規模のチームを率い、AWSの導入や運用標準の策定にも携わっていましたが、自身の手を動かす機会は次第に減っていきました。
このまま“管理専門”になっていくことに違和感があり、技術の最前線に戻る選択肢を探していたところ、クラスメソッドの求人に出会いました。
面接前には、ブログや登壇動画を徹底的に読み込み、「現場感覚を取り戻したい」という思いを強く持って臨みました。
一次面接では、過去のプロジェクト経験やチーム運営に関する質問が中心で、自分の強みを素直に話せたと思います。
ただ、面接官から「今後はどの程度までプレイヤーとして手を動かしたいか」「技術的なキャッチアップはどのようにしているか」と聞かれた際、言葉に詰まりました。
ここ数年はアーキテクチャ設計やレビューが中心で、コードや構築手順を自分で実践することは減っていたからです。
「今後はキャッチアップしていきたい」と伝えましたが、面接官は少し厳しい表情をしていたように感じました。
その後の質問も、より具体的な技術スキルやハンズオン経験にフォーカスしており、私のキャリアとは若干ズレを感じました。
数日後、不採用の通知が届きました。
自分なりに前向きに取り組んだつもりでしたが、企業側が求めていたのは「今まさに手を動かしている技術者」であり、私のような“技術志向のあるマネージャー”とは少し方向性が違っていたのだと思います。
今回の面接で学んだのは、企業の求める人物像と自分の立ち位置をきちんとすり合わせることの重要性です。
技術への思いがあっても、それをどのレベルで、どのように現場で発揮するかが具体的でないと、意欲は伝わっても信頼は得られないのだと実感しました。
今後は、自分が“何をやりたいか”だけでなく“今できること”をしっかり棚卸しし、求められるポジションとのギャップを正直に受け止めて転職活動を進めたいと思います。
仮想体験談:独学の限界、質問の“意図”を読み違えた失敗
地方の中小IT企業で7年ほどインフラエンジニアをしていましたが、今後はよりAWSやIaCを活用した先進的な環境に身を置きたいと考え、転職活動を始めました。
クラスメソッドは技術ブログで知っていて、自分でもTerraformの勉強をしていたこともあり、興味を持って直接応募しました。
転職エージェントは使わず、自力で書類を作成し、企業サイトにある社員インタビューや会社説明資料を読んで面接に備えました。
最初の録画面接は何とか通過し、一次面接はオンラインで実施されました。面接官はエンジニアの方で、比較的フラットな雰囲気でした。
技術に関する質問では、「最近使ったAWSサービスとその選定理由」や「構築における工夫や失敗談」など、想定していたよりも一歩踏み込んだ内容が多く、かなり焦ってしまいました。
私は、学習した知識を中心に答えてしまい、「本当に現場で使ったことがあるのか」と疑問を持たれてしまったような空気を感じました。
また、「今後どんな技術領域に挑戦したいか?」という質問に対して、「とにかく幅広くチャレンジしたい」と漠然と答えてしまい、熱意が空回りした感覚が残りました。
面接後、3日ほどでお祈りメールが届きました。
自分ではある程度うまく話せたつもりでしたが、冷静に振り返ると、質問の“意図”を理解せずに表面的に答えてしまった点が多々あったと思います。
面接官は、技術的な深さだけでなく、考え方や判断のプロセスを見ようとしていたのに、それを汲み取る力が不足していました。
さらに、エージェントを使わずに進めたことで、面接対策や企業理解が独りよがりになっていたと痛感しています。
今後は、客観的なフィードバックをもらえる環境を活用しつつ、企業ごとの質問意図を想定した準備を重ねていきたいと思います。
クラスメソッド株式会社の面接でよくある質問とその対策
Q. なぜクラスメソッドを志望したのですか?
A. 単に「AWSに強いから」といった表面的な理由ではなく、自分のキャリアプランと企業の文化・技術領域がどのように重なるのかを具体的に伝えることが重要です。例として「発信文化に共感しており、自身も勉強会やブログを通じて技術を共有していきたい」などが効果的です。
Q. 最近興味を持って学んでいる技術やサービスは何ですか?
A. 単なる技術名の列挙ではなく、「なぜその技術に取り組んでいるのか」「どのように学習しているのか」「どんなアウトプットをしているのか」まで含めて話すと説得力が増します。業務との関連性があるとなお良いです。
Q. AWSで扱ったことのあるサービスを教えてください
A. 実際に使った場面やプロジェクトでの役割を交えて説明します。「EC2を使いました」ではなく「EC2を使ってテスト環境を構築し、CloudWatchで監視設定を行いました」など、具体性があると評価されやすくなります。
Q. 技術的なトラブルが発生したとき、どのように対応しましたか?
A. 問題発生時の状況・判断の優先順位・チームとの連携・結果の振り返りを含めて伝えると効果的です。たとえば「ユーザー影響を最小化するため一時的に冗長構成を切り替え、原因調査と恒久対策を並行で進めました」といった流れが好まれます。
Q. チームでの開発や構築において意識していることは何ですか?
A. 自分の作業範囲だけでなく、チーム全体の進行やレビュー文化にどう貢献しているかを示すと良いです。「定例MTGで進捗だけでなく構成の相談を積極的に持ちかける」「ナレッジをドキュメント化してチーム内で共有する」などが効果的です。
Q. 自己紹介を簡単にお願いします
A. 経歴の説明に終始するのではなく、「どんなエンジニアとしてキャリアを積んできたか」「今後どう成長していきたいか」といった要素をコンパクトに織り交ぜると印象が良くなります。30秒~1分程度で収めるのが理想です。
Q. クラスメソッドのブログなどを読んだことはありますか?
A. はい/いいえの回答にとどまらず、「どの記事が印象的だったか」「なぜその内容に惹かれたか」まで話せると、企業理解と興味の深さが伝わります。読んだことがない場合は、正直に話した上で今後読みたい分野に触れるのが望ましいです。
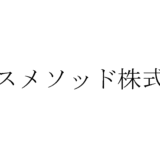 クラスメソッドの面接に落ちた方の体験談【法人営業編】
クラスメソッドの面接に落ちた方の体験談【法人営業編】 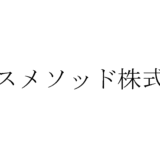 クラスメソッドの面接に落ちた方の体験談【Webエンジニア編】
クラスメソッドの面接に落ちた方の体験談【Webエンジニア編】
面接で落ちて後悔しないために。転職エージェントという選択肢
さて、ここまでこの記事をお読みいただいたあなたは、これから就職や転職を考えている方、あるいはすでに面接を控えている方だと思います。そして、就職や転職活動において事前準備をしっかりと行うことは非常に重要なので、その準備のためにこのブログをじっくりと読んでいただいているのだと思います。
そして、落ちた方のエピソードをまとめていた中で、気づいたことがあります。
それは、
企業研究や自己PRなどの事前準備はしっかりできていても、圧倒的に面接の練習が足りず、面接に落ちてしまったケースが多かった
ということです。
対人相手に実際に話してみる経験を積むことは非常に重要です。

自分の頭の中で「こう話そう」とシミュレーションするのは簡単ですが、それを実際に相手に伝えることは全く別のスキルです。
特に、面接の場では緊張やプレッシャーも影響し思うような受け答えができず落ちてしまうケースが非常に多いです。
今回の記事には書ききれなかったエピソードも多々ありますが、共通して感じたのは「圧倒的に面接の練習が足りない事が原因で落ちてしまい、後悔している方が非常に多かった」ということです。

「企業研修はばっちり」「説明会にも参加しました」と、準備を万全にして臨んでも、面接の練習が足りず、自身の実力や思いを伝えることが出来ずに不合格で終わってしまうことが多々あります。
そのため、内定を獲得するために面接の練習を実践に近い形で行うことをお勧めしますが、家族や友人に面接の練習をお願いするというのはお勧めしません。
家族や友人もこちらが満足するまで何時間も面接の練習に付き合ってくれる訳ではないでしょうし、仮に付き合ってくれたとしてもこちらが気を遣ってしまいますよね。本当はもっとやりたいのに遠慮して「もう大丈夫」と言ってしまうかもしれません。
それに、家族や友人は面接のプロではないので、適切なフィードバックを受けるのは難しいです。
 やはり本気で準備をして内定を獲得したいのであれば、気兼ねなく自分が納得できるまで何度も面接の練習ができる転職のプロの方に相談した方が安心できますよね。
やはり本気で準備をして内定を獲得したいのであれば、気兼ねなく自分が納得できるまで何度も面接の練習ができる転職のプロの方に相談した方が安心できますよね。
従って、本気で内定を獲得したいのであれば、転職のプロである転職エージェントの活用をすることをお勧めします。転職エージェントは就職活動や転職支援のプロフェッショナルです。転職を成功させるための面接対策について、客観的かつ合理的なアドバイスをしてくれます。
彼らは「転職」「就職」を成功させることを仕事にしており、あなたが面接に合格することが彼らの成果となり、それで転職エージェントの方はお金をもらっているのです。
彼らは私たちを紹介する事でお金をもらっているので、お金が欲しいから私たちを受からせたいのです。面接の練習を何回もしてでも、私たちに内定を獲得して欲しいのです。

あなたが合格する事が転職エージェントの目標であり、そのために、真剣に、そして全力でサポートしてくれます。
転職エージェントを使うことで、自分の弱点をプロの視点から分析し、内定を獲得するチャンスが得られます。
しかも、転職エージェントは私たちが内定を獲得する事でお金をもらうことが出来るので、私たちはお金を一切払う必要がありません。
転職のプロに面接の練習をお願いすることが内定の一番の近道ですし、しかも無料…お得なのでぜひやった方が良いですし、そんな彼らを使わない理由は全く無いですよね。
転職エージェントは無料で活用できるため、プロのサポートを無料で受けられるこの機会を活かさない手はありません。成功への一歩を確実にするためにも、転職エージェントに登録することを強くお勧めします。
📌 特におすすめの転職エージェントはこちら
👉
👉
あなたの転職活動が成功し、理想のキャリアを築けることを心から願っています。
「私も落ちた」「こんな質問に困った」——そんなエピソードも大歓迎です。経験を共有することで、次の誰かが自信を持てるかもしれません。ご協力いただける方は、ぜひコメント欄や問い合わせフォームからお気軽にお送りください。
※投稿された内容は、記事の中で「仮想体験談」や「面接傾向」として参考にさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。また、お寄せいただいた内容は編集の上、匿名で掲載させていただく場合がございます。